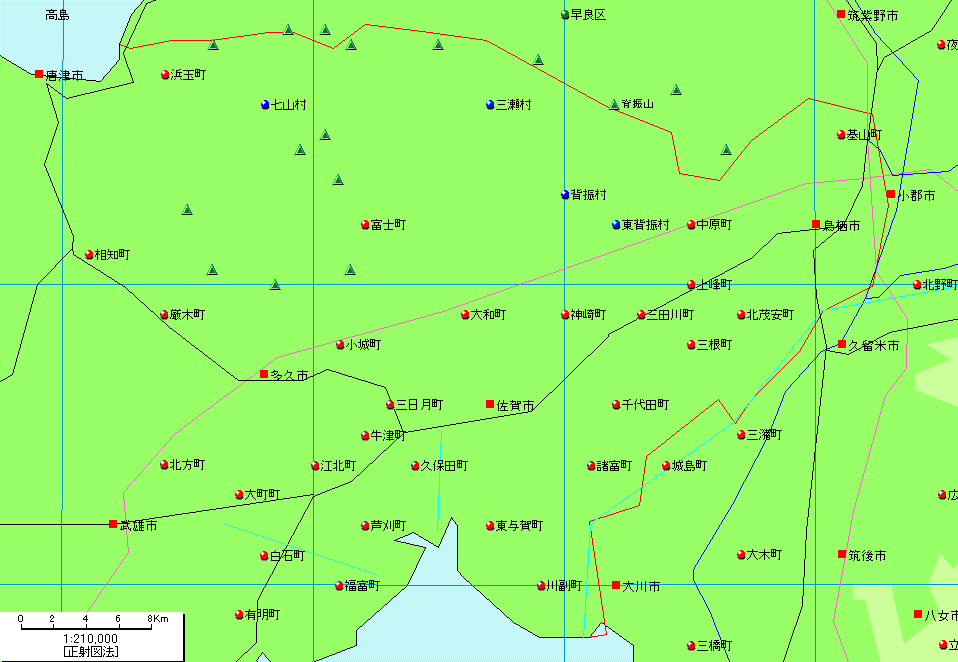
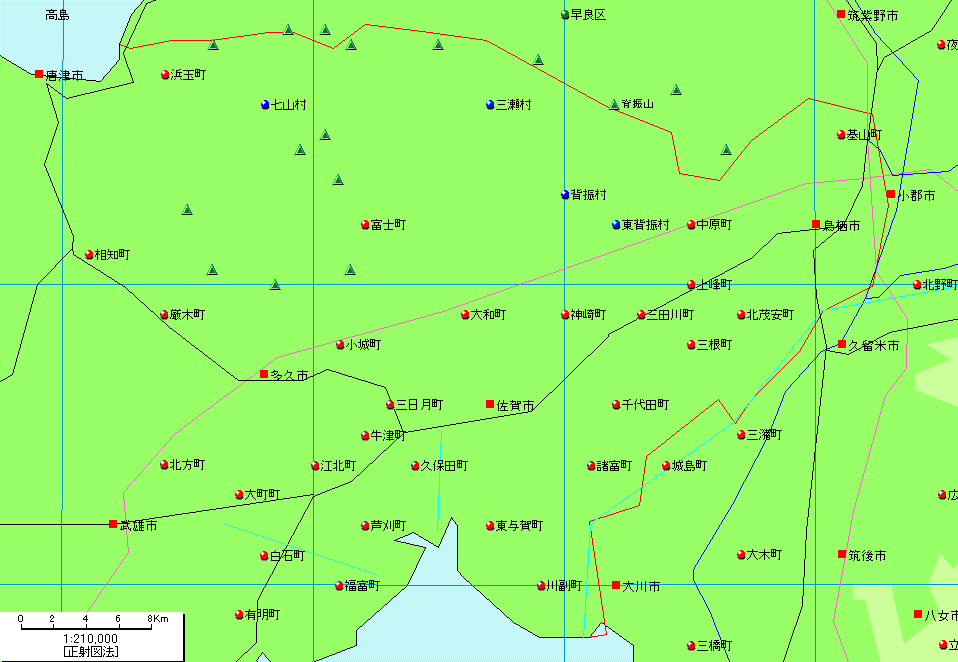
佐賀県三養基郡 【トピック】2005/03/01 三養基郡中原町、北茂安町、三根町が合併して誕生 -------------- 旧三養基郡中原町のデータ ------------------- 【いわれ】蓑原村と原古賀村が明治22年4月1日に合併し中原村となった。一説によれば中国の中原に由来したともいわれている    
【シンボル】花(桜)、木(ハゼ)、鳥(なし) 【日本一】小学校天体望遠鏡(ドーム式) 小中学校のLL・ML・AN教室 風の里    
【観光】 行列浮立(はぐま、やり、鉄砲などを連ねる。実施日9月23日) 体育センター 鷹取山から見る町の全景(この地方には藩政末期頃からハゼの木が植えられ、町内にも3軒のロウ屋があって、鷹取山の中腹は一面ハゼの木で覆われている。紅葉の季節には山が紅く染まったように色づく) 風天山(綾部神社の宮山として知られている。斜面には桜やつつじが植えられ春爛漫の景色を楽しむことが出来る。頂上からは筑後川を望む) 綾部宮山の桜(3月下旬) 綾部宮山のツツジ(5月初旬) 綾部城址 綾部神社(綾部城址の東麓にあり風の神を祀る神社) 旗あげ神事(綾部神社。樹齢700年の大木イチョウのこずえに35cmのアサの旗(神旗)を上げ旗おろし迄の間の旗の巻き上がる状況で風水害や豊作を占う。実施日7月15日) 旗おろし神事(綾部神社。相撲を取らせた後、旗を降ろし、風水害や豊作を占う。実施日9月24日) 町立図書館 姫方前方後円墳 総合センター 働く婦人の家 町民祭(文化の向上と農業、商工業の振興。実施日11月) 姫方遺跡 町南遺跡 原古賀三本谷遺跡 白坂公園の桜(3月下旬) ハゼの紅葉(11月上旬) ほんげんぎょう(鬼火たき) 中原公園   
【名産】 ぼたもち(この餅の始まりは鎌倉時代に綾部の地頭が源頼朝に従い、奥州征伐で活躍したお祝いの餅として兵士に振る舞ったことに由来し、たっぷりとこし餡がまぶされ素朴なおいしさ) ムツゴロウまんじゅう ミカン ジネンジョ 【方言】 おばっちゃん(おばさん) おぎゃんと(そんなこと) おとん(お前、君)-------------- 旧三養基郡北茂安町のデータ ------------------- 佐賀県三養基郡 【いわれ】土木治水の神として知られる偉人、成富兵庫茂安公の名にちなんで 【シンボル】花(スイセン)、木(キンモクセイ)、鳥(なし) 【観光】 白石陶器祭り(商工会を中心に実施9月21日から25日) 六ノ幡遺跡 筑後大堰 おかゆ祭り(おかゆだめし。千栗八幡宮で行われる日本3大かゆ祭りの1つで、2月下旬に大鍋でかゆを炊き、箸を十文字に渡して肥前、肥後、筑前、筑後の四ヶ国に国分けして箱に納める。3月15日に取り出し粥に付くカビの付き方によりその年の天候、豊作などを占うもの。実施日3月15日) 奉納浮立(千栗神社の放生会に浮立を奉納するもので、鐘、太鼓、笛、さいのけがみみこしの供をして行列浮立を行う。実施日9月15日) 大塚古墳 宝満神社前方後円墳 白石神社磁製灯ろう 白石神社(祭神は鍋島藩の鍋島直弘公だが、治水に功績があった成富兵庫茂安公が大正15年に合祀された。境内には明治18年に作られた白石焼の磁器製灯籠があり神社周辺は緑が多く春は桜、秋は紅葉と楽しめる) 千栗八幡宮(一の石鳥居をくぐり石段を上がり境内にはいると中世以降、肥前国一宮と呼ばれる由緒ある神社がある。応神天皇、仲哀天皇、神功天皇が祭られている。神亀元年に壬生春成が創建した九州5社八幡の一つ) 大島池の跡碑(大ガメがいるといわれた池の跡) 茂安公築堤功績碑 清流の里 【名産】 白石焼き(「とびかんな」「象がん」など独特な味わいのある陶器。文化3年白石鍋島藩は伊万里大川内から陶工を呼び寄せ、北茂安白石で御用窯を命じたのが始まり。江戸時代京都の陶工・臼井走波を招き今の作風が確立。9軒の窯元があり民芸陶器) 三養基トマト(完熟トマト) 高菜漬け 酒(天吹) 【方言】 こすか(けちな) さんにょう(計算) そいばってん(しかしながら) こいば(これを)-------------- 旧三養基郡三根町のデータ ------------------- 佐賀県三養基郡 【いわれ】「肥前風土記」に「景行天皇行幸のときこの村にお泊まりになって夜素御寝(やすみね)と仰せられて安眠された。そこでこの村は御寝安(みねやす)村がよいということで御寝と名付けた。今字を改めて三根となす」とある。 【シンボル】花(カンナ)、木(モチ)、鳥(なし) 【観光】 筑後川河畔公園(九州第1の河川で坂東太郎(利根川)、吉野三郎(吉野川)と共に「筑後次郎」とも呼ばれている) 筑後川河川敷の第3セクターによるゴルフ場 町営総合グラウンド(スポーツ公園) クリーク周辺の町民憩いの場(三根クリーク公園は町の象徴であるクリークを利用した公園で真っ赤なザリガニの形をした橋が目印。クリークに棲むフナやザリガニなどの生物の観測地がありカヌー教室も) 三根ふるさと祭り(実施日11月中旬) 的射祭(実施日2月17日) 江見沖神事(実施日9月12日に近い日曜日) 本分貝塚(弥生時代中期前半から中期後半の貝塚) 薬師如来座像(光浄寺鎌倉後期から南北朝期の木像) 地蔵菩薩立像(長泉寺平安末期の檜一木像) 鐘楼門(西念寺文化2年上棟の鐘門を合わせた二層構造の門) 仏足石(西念寺) 筑後川の堤防でのつくし摘みを楽しむ行楽客の風景 浮立(五穀豊穣を祈る。実施日10月の20日に近い日曜日) イグサの植え込み風景(12月上旬) カササギ生息地(カチガラス。国指定天然記念物) 成富兵庫茂安公記念碑(国道264号線沿いにある。慶長年間、北茂安町千栗から三根町坂口まで12に及ぶ大堤防を築き筑後川の治水に功績を残した) 【名産】 六田旭豆(炒ったエンドウ豆に白い砂糖の衣がまぶされほのかな生姜風味が特徴) 銀月まんじゅう い草 アスパラガス イチゴ、 エツ(日本では筑後川にしかいないカタクチイワシ科の珍魚) 【方言】 ほとめく(もてなす、歓迎する) おとん(お前) とぜんなか(手持ちぶさた、寂しい) ととしか(不器用) にくじ(悪口、いたずら) |